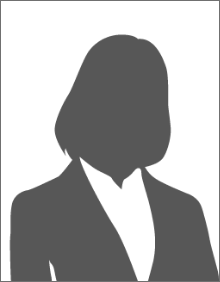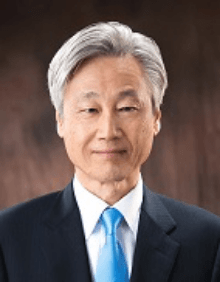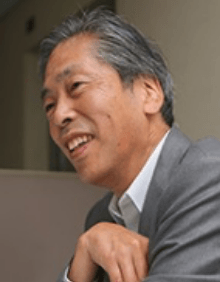弁理士法人レガート知財事務所 弁理士
峯 唯夫 先生
商標の剥離抹消行為は商標権侵害となり得るのか
■ ローラーステッカー事件
商標の剥離抹消行為についての判断を示した「ローラーステッカー事件」(大阪高判令和4年5月13日、令和3年(ネ)第2608号)」は、次の通り判示し、商標権侵害を否定しています。
「商標法の目的は、信用化体の対象となる商標が登録された場合に、その登録商標を使用できる権利を商標権者に排他的に与え、商品又は役務の出所の誤認ないし混同を抑止することにあり、商標権侵害は、指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で、商標権者以外の者が、登録商標と同一又は類似の商標を使用する場合に成立することが基本である(商標法25条、37条)。すなわち、商標法は、登録商標の付された商品又は役務の出所が当該商標権者であると特定できる関係を確立することによって当該商標の保護を図っているということができる。
商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通させる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止することは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。したがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害を構成するとは認められないというべきである。」
■ 何が問題なのか
「メーカーAが商品の包装に付した商標αを、中間業者Bが剥離し、自己の商標βを付して販売し、最終需要者Cが購入した」という事例設定で、問題点を考えたい。
中間業者Bは、メーカーAの商品であると認識して購入する。
中間業者Bは、商標βを付すことにより、「Bの商品」として市場に出している。
最終需要者Cは、中間業者Bの商品であると認識して購入する。
このとき、最終需要者Cにおいて、商標に起因する「出所の混同」は生じていない。なお、商品自体はメーカーAの商品なので、これを中間業者Bの商品であると認識した最終需要者Cは、「商品を混同」しているといえる可能性はあるが、これは「商標による出所の混同」ではない。
このとき、メーカーの立場としては、商標の抹消行為によって、自己の商品であるという情報が最終需要者Cに伝わることが阻止された、すなわち、メーカーの商標についての「業務上の信用」の化体が阻害された、いうことになるのだろう。
■ 商標法の枠組みとの関係
商標には、自他商品識別機能を前提として、出所表示機能、品質保証機能、広告機能があるというのが一般的な理解であろう。商標は、商標に起因する出所の混同を防止することを通じて、商標の持つこれらの機能を保護している。商標法が禁止するのは、出所の混同を惹起させる行為である。第三者による「商標の使用」に起因する「出所の混同」を防止することで、「商標を使用する者の業務上の信用の維持」をはかるというのが、商標法の枠組みであると理解できる。
商標は、「商標の機能を阻害する行為」のすべてを規制しているものではない。上掲判決の説示するとおりと考える。
■ マグアンプ事件
「商品の小分け」についての事件として有名な「マグアンプ事件」(大阪地裁平4(ワ)11250号 平6年2月24日判決)は、傍論ではあるが次のように説示している。
「商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の中途で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を中途で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成するものといわなければならない。」
商標機能論に立ったものであろうが、商標法の枠組みを超えているように思う。
■ どうしたらよいか
商標を使用する者は、自己の商品は、自己が付した商標がそのまま保持された状態で、最終需要者まで届くことを期待している。「商標が付された状態で最終需要者に届く」ことによって、商標に業務上の信用が化体するのであるから、「商標が付された状態で最終需要者に届く」ことは、「法律で保護される利益」といえる。また、このようなことは、商道徳、商慣習として確立しているのであり、流通過程において商標を抹消する行為を正当化する根拠はない。
したがって、中途において商標を抹消する行為は不法行為(民法709条)に該当すると考えることができるだろう。