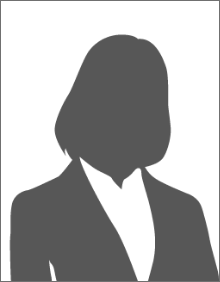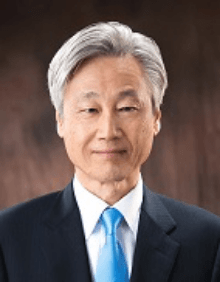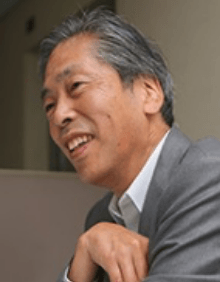首都大学東京 法科大学院 元教授 元弁理士 工藤 莞司 先生
チョコレート菓子の立体商標の登録例
使用による識別力の獲得
先日、チョコレート菓子「ポッキー」が立体商標登録!発売から60年、悲願達成と報じられた(8/7(木) 20:29配信TBS)。
 江崎グリコの「チョコレート菓子」の立体商標で、担当者のご苦労の成果とある。調べると、令和7年7月25日登録の登録第6951539号で、商標法3条2項適用とあり、使用による識別力の獲得が認められたものである。ネット情報にも、チョコレート菓子マーケティングリサーチ会社によるインターネット調査で、調査対象の日本国内に居住する男女(16歳~79歳)を対象に、年齢ごとの人口構成比に合わせた割付を行い 1,036 人から回答を得たとあり、これが有利に影響したのであろう。
江崎グリコの「チョコレート菓子」の立体商標で、担当者のご苦労の成果とある。調べると、令和7年7月25日登録の登録第6951539号で、商標法3条2項適用とあり、使用による識別力の獲得が認められたものである。ネット情報にも、チョコレート菓子マーケティングリサーチ会社によるインターネット調査で、調査対象の日本国内に居住する男女(16歳~79歳)を対象に、年齢ごとの人口構成比に合わせた割付を行い 1,036 人から回答を得たとあり、これが有利に影響したのであろう。
使用による識別力の獲得を直接に証明するものはなく、販売や広告実績の外に、最近ではアンケート結果が利用されて、客観的なものは採用される例も多いようである。本件でも、この点での担当者のご苦労が結実したのであろう。
「ひよこ立体商標」事件の例 ここで、思い出されるのが「ひよこ立体商標」事件(平成18年11月29日 知財高裁平成17年(行ケ)第10673号)である。
 指定商品「まんじゅう」について立体商標「ひよこ」は登録になったが、その後無効審判でその有効性が争われて不成立審決の取消訴訟では商標法3条2項の適用が否定された事例である。本件商標「ひよこ」は、指定商品「まんじゅう」の形態自体について、被告(商標権者)の店舗が九州北部、関東地方等に所在して全国的に存在するものではないこと、その宣伝広告は文字商標「ひよこ」に注目する形態で行われていること及び極めて類似した菓子が全国に多数存在し和菓子としてはありふれた形状のものであることを理由として、全国的な周知性の獲得を否定したものである。商標法3条2項の適用については、日本全体を基準、すなわち全国的な周知性の獲得を基準とするとの解釈を示した。この知財高裁の判決の影響で、特に立体商標の使用による識別力の獲得には厳しくなっているように思われる。この判決の全国的な周知性基準は疑問で、妥当ではないとするのが私見である(拙著「商標法の解説と裁判例」改訂版103頁)。
指定商品「まんじゅう」について立体商標「ひよこ」は登録になったが、その後無効審判でその有効性が争われて不成立審決の取消訴訟では商標法3条2項の適用が否定された事例である。本件商標「ひよこ」は、指定商品「まんじゅう」の形態自体について、被告(商標権者)の店舗が九州北部、関東地方等に所在して全国的に存在するものではないこと、その宣伝広告は文字商標「ひよこ」に注目する形態で行われていること及び極めて類似した菓子が全国に多数存在し和菓子としてはありふれた形状のものであることを理由として、全国的な周知性の獲得を否定したものである。商標法3条2項の適用については、日本全体を基準、すなわち全国的な周知性の獲得を基準とするとの解釈を示した。この知財高裁の判決の影響で、特に立体商標の使用による識別力の獲得には厳しくなっているように思われる。この判決の全国的な周知性基準は疑問で、妥当ではないとするのが私見である(拙著「商標法の解説と裁判例」改訂版103頁)。
このように商品の形態については商標法3条2項の使用による識別力の獲得が必要な中で、この度の登録は、審判や審決取消訴訟を経由しない登録で、評価されよう。この点での担当者のご苦労が窺われる。そして、本件チョコレート菓子のブランドのみならず、企業としてのステータス等にも貢献するであろう。因みに、「チョコレート菓子」については、最近の登録例に「きのこの山」(登録第6031305号)、「たけのこの里」(登録第6419263号)がある。