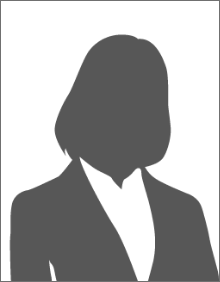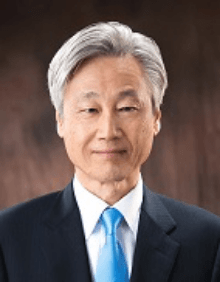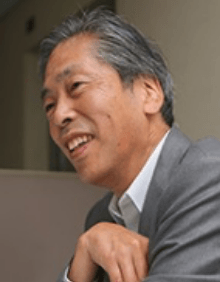首都大学東京 法科大学院 元教授 元弁理士 工藤 莞司 先生
商標法4条1項6号の趣旨等について
知財高裁の解釈と問題点
立法趣旨について 最近の知財高裁の裁判例に、商標法4条1項6号事案で、その趣旨は、同号に掲げる団体の公益性に鑑み、その権威、信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護することと解されるとしたものがある(令和7年3月12日 知財高裁令和6年(行ケ)第10090号 「ぽんちゃん」事件、同旨令和7年2月4日 知財高裁令和6年(行ケ)第10060号「JPCスポーツ教室」事件)。同号案件は少なく稀有な事案で、その中での裁判所の解釈である。
この裁判例は、「出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護すると解される」としたが、疑問である。商標法4条1項6号は、そのような規定振りではなく、出願商標の指定商品・役務にかかわらず適用可能な規定である。出所の混同を防ぐ、商標法4条1項15号等は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同・・・」と規定している。10号、11号も商品又は役務を問題としている。そもそも6号は、不登録事由としての位置からも明らかなように、公益的不登録事由であって、無効審判の請求については、除斥期間はない(47条1項)。調べると先の裁判例(平成21年5月28日 知財高裁平成20年行ケ第10351号 「ISOマウントエクステンダー事件」)があり、これが影響していると思われる。
著名なものについて また、この裁判例は、商標法4条1項6号にいう「著名なもの」というためには、同号に掲げる団体や事業の地域性に照らし、必ずしも日本全国にわたって広く認識されている必要はないが、なお相応の規模の地理的範囲において広く認識されていることを要するものと解するとした。直前の裁判例(前掲「JPCスポーツ教室」事件)も本号の「著名なもの」については、同項10号の「需要者の間に広く認識されている」(いわゆる広知性)と整合的に解釈するのが合理的であるとしたが疑問である。
6号の「著名」で、問題になるのは、実務上使用される周知・著名商標との異同であるが、これらとは明らかに区別されるべきである。法律上、周知・著名商標については、「需要者間に広く認識されている商標」と規定している(4条1項10号、64条1、2項)。6号の「著名」とは異なるものである。以前、私見として、当該団体の標章として特定できる程度に一般に知られているとの解釈は広すぎるだろうかと書いた(拙著「商標法の解説と裁判例」改訂版113頁)。4条1項8号の「著名な略称等」も同様であるが、最高裁は「本人を指し示すものとして一般的に受け入れられているか」(「国際自由学園事件」平成17年7月22日 最高裁平成16年(行ヒ)第343号 判例時報1908号343頁)を基準として、著名商標等とは画して解している。関連文献(イベント開催情報)等への登載からの認定となろう。少なくとも、取引者、需要者の認識の問題ではない。
結局、この判決では、「館林市民にはなじみのあるキャラクター(編注右掲参照)として広く認識

されていると認められ得るものの、館林市外への露出は散発的かつ限定的であり、群馬県の総人口約197万人に対して館林市の人口が8万人弱にとどまること(平成28 年4月1日現在)からしても、群馬県及びその周辺において広く認識されていると認めるには至らないとして著名を否定した。結論に異論はないが、6号らしい基準を示して欲しかった。
最近商標法4条1項6号に係る審判決例が出始め、是非関心を持って検討して欲しい。