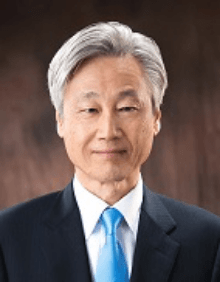首都大学東京 法科大学院 元教授 元弁理士 工藤 莞司 先生
「氷山印事件」判例再考
=本件判例と現行法=
先般、ある会合で、商標の類似について話す機会があり、その時「氷山印事件」判例の現在的意義はどうかと問われた。
本件判例のポイントは、①商標の類否は、同一又は類似の指定商品に使用された場合における、出所の混同の虞の有無で決すべき。②指定商品の具体的な取引の実情に基づく。この場合、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的な考察を要し、離隔観察前提で、③外観、観念又は称呼の類似は出所の混同の虞を推測させる一応の基準で(最高裁昭和39年(行ツ)第110号 昭和43年2月27日 民集22巻2号399頁)、未使用商標同士はこの③基準とされる。
考慮されるべき取引の実情
取引の実情については、直後に「氷山印事件」判例のいう取引の実情とは指定商品全般の一般的、恒常的なものと解した最高裁判決(「保土ヶ谷化学社標事件」がある(昭和49年4月25日 最判昭和47年(行ツ)第33号 審決取消訴訟判決集昭和49年443頁)。しかし、東京高裁(知財高裁)の裁判例は、当事者一方提出の証拠から認定して、本願商標に係る個別具体的な取引の実情の下では混同の虞なしとして、商標非類似と判断して、審決を取り消す事案は少なくない。そもそも審査、審判においては職権主義であり、法も商標の類似判断においては、使用証拠を求めるところではない。この点、最近、特許庁は、商標審査基準において、「指定商品又は指定役務の一般的、恒常的な取引の実情」と明記した(4条1項11号1.(1))。裁判所の賛同が期待される。
現行4条1項11号との整合性
本件判例は旧商標法(大正10年商標法)下のもので、「対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合、商品の出所の混同を生ずる虞があるか否か」としており、商標の類似判断基準というよりは、旧法2条1項9号の規定の趣旨を言っているのではないかとも読める。すなわち、商標の類似自体ではなく、同一又は類似の商品への使用をも条件として、出所の混同の虞を判断するとし、そうとすれば、非類似商品間での商標の類似は考えられないこととなってしまう。
しかし、現行法は、4条1項11号以外でも、例えば、同1号等でも、「国旗と同一又は類似の商標」と規定し、19号も商標自体の類似を規定している。少なくとも、現行法では、指定商品への使用を前提にしない商標自体の類似を規定しているとみられ、常に、「同一又は類似の商品に使用した場合」を条件とする本判例は、現行法4条1項11号とは整合していないとの疑問が生じる。
本件判例は、現在では、審決取消訴訟事件のみならず、侵害訴訟事件の商標の類似判断の前提として、必ず引用される。そこでは、取引の実情は、指定商品・役務の一般的、恒常的なものと解し、また、少なくとも現行法下では、商標自体での類似を考えるべきと思う。
本件判例は、判決後50年にも至り、商品・役務の多種・多様化と共に、著しく取引形態が進展し、変化している現在であり、また現行法の規定にも従った見直しは必要と思われる。