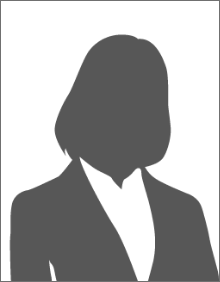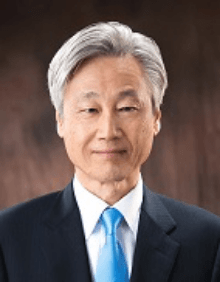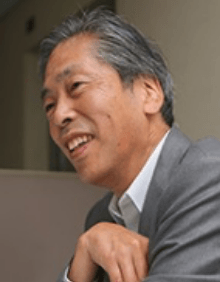弁護士法人窪田法律事務所 弁理士 加藤 ちあき 先生
声の権利
「ちあきさん、お説教と昔話と自慢話は絶対しちゃいけないって高田純次さんが言ってますよ」と、若い友人からお小言を賜ります。その3つを取ったら私には何も残らない気がしますが(笑) お説教と自慢話はさて置いて 旧い友人と思いっきり昔話をするのはとても楽しいものです。
今年のWIPO(国連の世界知的所有権機関)のイベントに小学校の同級生が登壇しました。幼馴染の晴れ姿を 同じ知的財産法のステージで拝めるなんて奇跡のようで この上なく幸せなことでした。小学校の仲間とは今でも時々会っては たわいもない話をします。かけがえのない時間です。
だいぶ大人になってから分かったことですが、その仲間の中に日本を代表する声優さんの息子Kくんがいました。渋い声で話しかけて下さる彼のお父さんは お洒落な芸術家風で 子どもながらに我々の親たちとは全然違う(カッコイイなぁ)と思っていました。
なぜ 突然Kくんパパのことを思い出したかといいますと、最近 日本を含む世界各国では「声の権利」の保護に関する議論がとても高まっているからです。
2024年11月13日、Kくんパパも生前所属していた業界の3団体が共同で記者会見を開き、生成AIによる音声について「アニメや外国映画などの吹き替えに使用しない」、「使用する際は本人の許諾を得る」、「生成AIであることを明記する」という3つの要望を打ち出しました。日本では人の「声」の保護について法が整備されておらず、団体は速やかなルール作りが必要だと訴えていました。
韓国では、2022年6月7日より「国内に広く認識され、経済的価値を持つ他人の姓名、肖像、音声、署名など、その他人を識別できる標識を公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自分の営業のために無断で使用することにより他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為と規定し、音声の無断利用行為が救済されることとなりました(同法第2条第1号タ目)。
中国では、2021年1月制定の民法典により、「自然人の声」を肖像権規定の対象に含めることによって保護しています(1023条2項)。
アメリカでは州法レベルではあるものの、テネシー州において「Ensuring Likeness Voice and Image Security Act(筆者仮訳:類似音声及び肖像の安全を確保する法律=通称エルビス法(ELVIS Act)」が成立し、今年の7月1日から施行されました。故エルビスプレスリーゆかりの地 テネシー州のこの法律は、個人の声を保護するだけでなく 個人の声や肖像を無許可でディープフェイク技術に使用した場合に、生成型AI事業者とインターネットプラットフォームの双方に責任を問うことができる根拠を設けています。この他、カリフォルニア州でも「声」をパブリシティ権として制定法で保護しています(California Civil Code § 3344(a))
現在、連邦の超党派上院AIワーキンググループでは、声を含むAIによって引き起こされる種々の問題に対処するための報告書を発表し、AI に関し、憲法修正第1条の原則に従って、名前・画像・似顔絵・音声の無断利用(unauthorized use of one’s name, image, likeness, and voice)から保護する立法の検討が勧告されています。
ところで、皆が口々に「声の権利」と議論しているものの中身は一体何なのでしょうか、例えば、「言葉」に近いものなのでしょうか?(参考:1973年ドイツ連邦憲法裁判所「自分の話し言葉に対する権利」(das Recht am gesprochenen Wort:BVerfGE 34, 238)) それとも、生きている人間(死者を除く)の「声」そのものなのでしょうか?個人的にとても興味があります。もし仮に「言葉」の権利に近いものとして捉えられる部分があるとすれば、声の商標登録(音の商標登録)によって一部守ることができる名台詞(決めゼリフ)のようなものも存在するのでは?と思っています。
他方で、こういう新たな技術の話をしますと、悪い点や怖い面ばかりが強調され、とかく禁止や制限の方向に議論が傾きがちです。しかし、進行性の病気で声を失った若い人気声優さんが、AIに声を学習させたことで引き続きSNS発信ができたり、「トップガン・マーヴェリック」という新作映画制作の際、旧作でライバル役だった俳優さん(喉の癌で声が出にくくなった)が、AIによってあたかも自身がしゃべっているかのように演技して出演できたり、という素晴らしい面があることにも注目する必要があります。
Kくんパパが長年演じたアニメキャラクターは私の理想の男性でした。そのキャラクターは別の声優さんによって今もスクリーン上で輝き続けています。でも、時折あのニヒルなKくんパパの声で映画を観たくなるのは私だけでしょうか…。前記で概観した各国の法制は亡くなった人の声の保護については規定していません。声の権利=声を守るということについて、今後も考え続けていきたいと思います。
以上