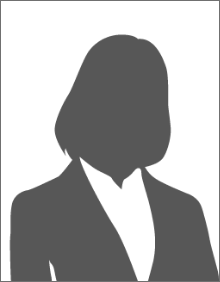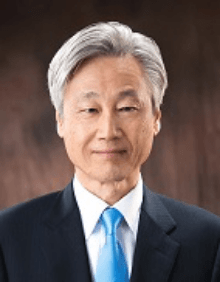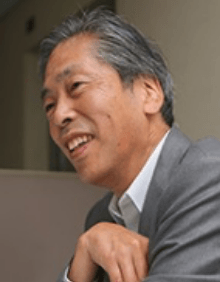弁護士法人窪田法律事務所 弁理士 加藤 ちあき 先生
Spread Our Wings!
弁理士の加藤ちあきと申します。これからこちらのコラムを担当します。どうぞよろしくお願いします。
好評を博したNHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」が今週で終ってしまいます。主人公のモデルとなった三淵嘉子さんは、我が母校明治大学の女子部から法学部へと編入された方であり、昭和15年(1940年)に日本初の女性弁護士となられました。今も神田須田町に実在する甘味処「竹むら」(ドラマでは「竹もと」)や、桂場さんが梅子さんのお団子にOKを出した瞬間に鳴ったニコライ堂の鐘の音など、私にとってすべてが懐かしく、きらきらと宝物のように輝いていた青春時代を愛おしんだ半年間でありました。
さて、突然ですがここで問題です。全ての士業の中で女性に最も早く門戸を開いたのはどの士業だったでしょうか?それは「弁理士」です。
知的財産法の世界では、明治17年(1884年)に商標条例が公布、翌年に高橋是清が起草した「専売特許条例」が発布・施行されました。明治32年(1899年)、不平等条約改正とひきかえに外国人にも特許出願を認める特許法が施行され、パリ条約に加盟したことをきっかけに弁理士の前身である「特許代理業者登録制度」が誕生しました。明治42年(1909年)「特許代理業者」から「特許弁理士」に、大正10年(1921年)「特許」が取れて現在の「弁理士」となりました。ちなみに当時、「弁理士」は「辨理士」と書き、「弁護士」は「辯護士」と書きました。弁理士の「辨」とは理(ことわり)のことであり、弁理士とは理屈をわきまえた人という意味でした。一方、辯護士とは言葉を巧みに操る人の意であり、辨理士と辯護士とはその漢字の成り立ちからも全く意味の異なる職業でした。
さて、そんな言葉を巧みに操る弁護士さんですが、ドラマをご覧になっていた方はお分かりのとおり、弁護士になるには大正12年(1923年)に施行された「高等試験司法科」を受験せねばなりませんでした。しかし、当時その受験資格には「男子に限る」という文言がありました。
朝ドラの主人公たちが高等試験の受験資格を得るために法改正を待たなければならなかったのとは対照的に、大正10年(1921年)施行の弁理士法には最初から性別要件がなく(弁理士法第二條には「帝國臣民又ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ外國ノ國籍ヲ有スル者ニシテ私法上ノ能力者タルコト」、「帝國内ニ住所ヲ有スルコト」、「辨理士試験ニ合格シタルコト」という3つの要件のみが規定)、昭和10年(1935年)、日本初の女性弁理士そして士業第一号の女性が誕生しました。
その方は井上清子(いのうえせいこ)さんという27歳の女性で、最終学歴は高等小学校卒業でした。士業の女性第一号ということで、新聞各紙にも大きく取り上げられたと記録が残っています。なかでも朝日新聞の記事には、「来年度からは婦人辯護士試験も開始されるといふ矢先、女性の世界にはく 虹の様な氣焔である。」と書かれていて、当時の熱気が伝わってくるようです。
井上清子先生はまるでドラマの中の「よねさん」のように常に紳士用スーツをお召しになっておられ、男装の麗人として度々紹介されていたことが私の記憶にも残っています。しかし、井上先生は周囲を拒絶するような方ではなく、周りには常に応援を惜しまない方々が男女を問わず数多くおられたと聞いています。性別も学歴も関係なく井上清子弁理士を誕生させた史実は、当時の知的財産法と弁理士の世界が大変先進的でウェルビーイングであったことを窺知するに足るものです。
筆者が弁理士試験に合格したのは井上先生の合格から60年後ですが、同期合格者117名のうち11名が女性でした。合格したばかりの私たちを入れてようやく女性弁理士の総数が170名になったと聞きました。現在の女性弁理士の総数は1,941名(2023年1月31日付日本弁理士会統計)、2022年の弁理士試験合格者の女性比率は約33%で、他の士業と比べても高いと評価されているようです。
来たる2025年、井上清子弁理士が誕生してから90年を迎えます。諸先輩方が道なき道を切り開いてくださったおかげで、知的財産法の世界は、女性でも男性でも文系でも理系でも能力のある者だけが評価される平等な世界でありました。弁理士を志した際に恩師から「弁護士や医師のところには困った顔をした人がやってくるが、弁理士のところには喜びに満ちた人がやってくる」との言葉を頂きました。けだし名言だと思います。これからもこの世界がずっと続いていきますようにと心から願っています。