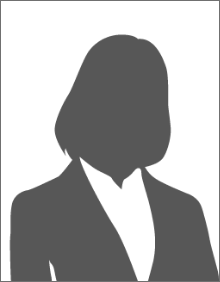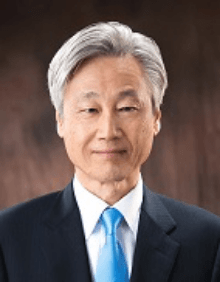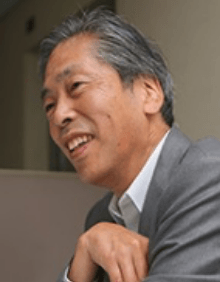一橋大学 名誉教授・弁護士 土肥 一史 先生
「村」の中の芸名
世間にはあまり知られていないと思うが、主としてエンタメ等の芸能界では、「著作権村」という言葉で、この世界の特殊性がいわれることがある。著作権「村」という言葉自体にも含意されるのであるが、閉鎖的な社会の独特なルールが妥当し、さまざまな場面で「村」の中での意思決定が図られる傾向を受けてのものだろう。
こうした村のルールに、本年9月30日、公正取引委員会と内閣官房は重い腰を上げ、「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を公表した。この指針で、問題となり得るさまざまな行動例があげられ、それらの適正化のために参考となる行動例もあげられている。そのひとつに「芸名・グループ名の使用制限」がある。実態調査において、実演家の芸名等に関する権利は、当該実演家が所属する事務所を退所した後も当該事務所に帰属する場合があり、退所する実演家に対して、それまで使用していた芸名等の使用が制限されることが確認されたとのことである。
これで想起されるのは、NHKの朝の連続ドラマ「あまちゃん」で茶の間をにぎわした「能年玲奈」さんが、所属事務所を退所した後、「のん」という芸名に変わった事例である。「能年」という氏自体、極めて珍しい氏であり、「能年玲奈」は本名であるらしい。筆者は確認できていないが、所属していた芸能事務所が、この「能年玲奈」を商標登録し、商標権の効力の下に使用を制限したからだとも伝えられている。
商標法26条には、商標権の効力は、「自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標」には及ばない、と明記されている。この「普通に用いられる方法で」については議論があろうが、芸能人が実演等での表記として普通に使用されていれば足りよう。EU商標制度の下いう、当該人物「による使用が営業又は取引における確立した慣行に従っている場合(共同体商標規則14条2項)」と同様に理解することでよい。
「能年玲奈」を元所属事務所が役務商標として登録していても、商標権者の有する商標権の効力は制限される。したがって、元所属事務所から独立した後も、「能年玲奈」を役務商標として使用することが禁止される法的根拠はないはずであるが、そうでないのがこの「村」のルールだったということだろう。仮に、芸能事務所と芸能人との間に使用を禁止する契約があっても、公序である商標法26条に反する契約として当然に無効と解すべきである。
なお、大相撲の四股名や歌舞伎・落語の名跡に関するルールは、商標制度が創設される以前から存在し、確立しているだろうから、別論ということになろう。もっとも、管見の限り、そこでは氏名が使われることはほぼなさそうではある。