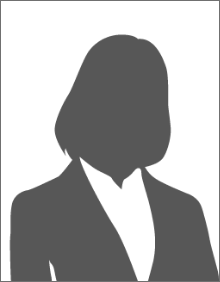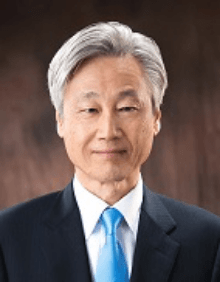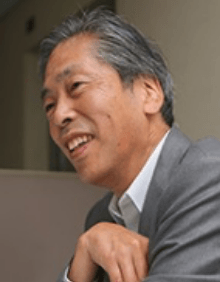一橋大学 名誉教授・弁護士 土肥 一史 先生
形式と実質
ビールの銘柄バドバイザー(Budweiser)は、チェコに由来するビールと米国で生産されたビールがあり、双方の間で商標を巡る長い紛争があった。チェコと欧州を中心とするバドバイザーと北米を中心とするバドバイザーの商標登録は、それぞれの地域では原則可能だ。欧州各国にはそれぞれの商標制度があり、米国には米国の商標制度がある。同一の商品について同一の登録商標は、国毎に並存し得る。属地主義の結果である。
しかし、国境を持たないネット上では、欧州の登録商標に基づく宣伝広告に米国からもアクセスできるし、その逆も然りである。では、米国のバドバイザーは、欧州・チェコのバドバイザーのネット上の宣伝広告を米国商標権の侵害と主張できるか。
ニコニコ動画で知られる動画配信サービスを提供するドワンゴ(原告・控訴人・被上告人)が、この配信システムに関する特許権に基づき、FC2ら(被告・被控訴人・上告人)に対する特許権侵害訴訟において、最高裁は、知的財産権の効力を自国内に限るという属地主義の原則を、柔軟かつ実質的に捉え判決した。FC2の提供する配信サービスもドワンゴの配信サービスも、動画の再生に併せてユーザによって書き込まれたコメントが表示される。違いは、FC2のシステムでは、日本国内ではなく米国にサーバが置かれていた。
最高裁は、それぞれのシステムを構築する行為を全体として実質的にみたとき、当該行為の一部が外国にあっても、わが国の領域内における実施に当たると評価し、当該行為にわが国の特許権の効力が及ぶとしたものである。
商標権の侵害は、権利者の許諾なしに、その指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に登録商標と同一又は類似の商標を使用することをいう。したがって、権利侵害の成否は、上記のネット上の宣伝広告が当該国内での使用と認められるかが問題となる。
この問題が争われた事案が「Sushi Zanmai」事件である。原告は、「すしざんまい・SUSHIZANMAI」の商標登録を有するつきじ喜代村。被告はシンガポールやマレーシアで食材等の輸入・販売を行う株式会社である。被告がウエブサイトで行う食材の宣伝販売行為が原告の有する日本の商標権を侵害するのかが、争われた。
知財高裁は、被告(控訴人)のインターネット上の宣伝広告はわが国での商業的効果を伴わないので、商標権の効力に関する「使用」とはいえないと判断した。その根拠を、2001年の「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」に求めている。
この共同勧告では、他国の商標の使用者がわが国でもビジネスを行っているか、わが国の顧客に商品・役務の提供を目的にしているか、使用されている言語はなにか、取引通貨はなにかといった諸事情を総合して、わが国での商業的効果の有無を実質的に判断し、侵害の成否を決する。
知的財産権の侵害の成否を実質的に判断することは、リアルの世界であると、ネット上であるとを問わず、当然に求められる要請であることに異論はなかろう。