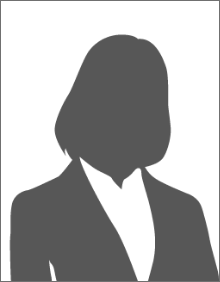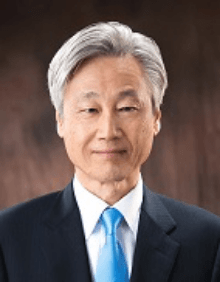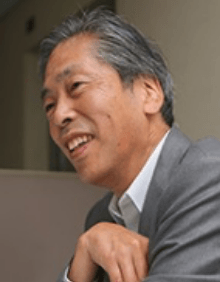一橋大学 名誉教授・弁護士 土肥 一史 先生
年寄りの昔話
ローマ法由来の法諺に、「自己の権利を行使する者は何人に対しても不法を行うものではない(Qui iure suo utitur nemini facit iniuriam)」というのがある。同時にローマ法には、「自己の矛盾する行為の主張は禁じられる(venire contra factum proprium)」というのもあり、これがドイツ法では信義誠実の原則、さらには権利失効の理論(Verwirkung)に、英米法ではクリーンハンドの原則につながっている。
70年ほども遡る昭和30年、東京高裁は、「多大の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至った商標『天の川』の名声を、自己の利益に用いんとし、たまたま訴外第三者(明治製菓)が所有し、全然使用していなかった登録商標『銀河』を譲り受け、これによって被控訴人(被告)の前記商標『天の川』の使用を禁圧しようとした」という事情の下では、かかる行為は権利の濫用として許されない、と判決した。商標権の行使が権利の濫用に当たるとした判断である。この判決以降、近くは令和5年の丸忠山田事件知財高裁判決まで、権利濫用論は商標権侵害紛争でしばしば登場することは周知の通り。
天の川事件で、明治製菓がその保有する登録商標「銀河」に基づいて類似商標「天の川」の使用差止を求めたら、「天の川」は止められたのではないか。この理により、成富信夫博士は、権利濫用論によるのではなく、権利失効の理論によって結論を導くべきである、との判例評釈を書かれている(別冊ジュリスト14号・昭和42年8月・有斐閣)。
商標法にとって一般法である民法1条3項で、「権利の濫用は、これを許さない」とあるから、商標権侵害訴訟においても権利濫用論の適用があることになんら不思議はない。ただ、民法166条2項で消滅時効の規定があり、債権又は所有権以外の財産権は時効にかかることを定めている。異論はあろうが、このことから所有権に基づく物上請求権も消滅時効には懸からないと解するのが妥当であろう。商標権が財産権であることは明らかだが、有体物ではない商標に関する権利を、所有権や占有権と同様に考えてよいかは、なおはっきりしない。
権利者が一定の期間を超えて権利を行使せず(時間的要素)、かつ債務者がもはや権利は行使されないと信頼することができる事情がある(状況的要素)場合、権利は失効し、その行使は認められない。これが権利失効論であり、時効のように一定の期間が経過しなくても、適用が可能であり、そこに権利失効論の存在理由があると、ドイツ連邦最高裁判所もいう。さらに、権利濫用論で求められている、他人に損害を加えること(Schikane)のみを以て権利を行使するとはいえない場合、権利失効論が機能する領域は確かにあろう。