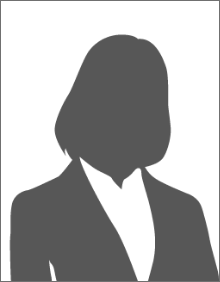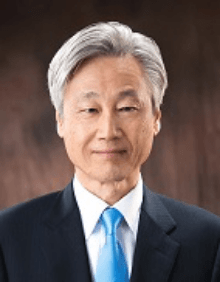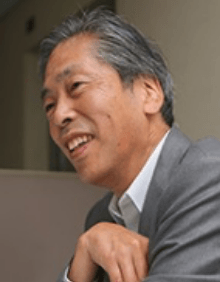一橋大学 名誉教授・弁護士 土肥 一史 先生
混同と連想関係
商標権に基づく裁判で争われる争点の1つに、商標の類否の問題がある。この問題を巡り最も多く引用される判決が、氷山印最高裁判決(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁)であるといっても過言ではなかろう。
この判決で、「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきである。それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」と述べている。
商標の類否は、先の判決によれば、2つの商標それ自体の属性を比較して、似ているかどうかを決めるのではなく、これらの商標が付された商品の出所の誤認混同の有無で決める。通例、この場合、形式的には2つの商標の外観、観念、称呼のいずれかひとつが一致するか酷似するかの関係がある場合、2つの商標は類似するとされているが、同時に、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきことも合わせ述べられている。
欧州商標法は、商標権の効力を、①商標と商品役務間のいずれにも、すなわち二重の同一がある場合、②混同のおそれがある場合、③著名商標の特別保護、正確には著名商標の識別力又は信用を正当な理由なく不正な方法で利用し又は害する場合について認める。②でいう混同のおそれには登録商標と比較対象標識が観念的に結合する関係、連想関係のある場合も含まれる。
この連想関係を混同のおそれに連結する考え方は、ベネルックス商標法に由来する。取引者が2つの商標の出所を混同すれば、混同された側は商品の売上が減少しよう。しかし、2つの商標の連想関係は取引者の記憶に蓄積されても、財の侵害には直接つながるものではない。
連想ないし観念的な結合関係と混同のおそれとは別の概念である。そのことは、氷山印最高裁判決でも、欧州商標法でも、所与のものとして理解されていよう。当該標識と登録商標の所有者との間になんらの関係も存在しないことを取引者・需要者が正確に認識していたとしても、当該標識から登録商標を観念的に想起する可能性はある。この可能性は、当該商標に結合したグッドウイルが他の商品提供者によって利用され、その者の標識にこれを移転する可能性を含んでいる。この点において、法律上の財の侵害を見る者は、ここに名声の冒用を認め、さらに、ネガティブな観念的結合関係による商標の価値評価の毀損を認めることにつながるのであるが、この連想関係の保護を商標法上認めることは、出所混同を奉る立場からの反発が容易に予想されよう。